日曜日の夜、赤ワインを飲みながらブログを書いている。
私はほぼ毎日、まず缶ビールを一本飲み、その後、冬は赤ワイン、夏は白ワインをグラスに一杯から二杯飲む。飲みすぎかどうかはわからないが、これが私にとっての心地よい酒量である。気持ちがゆったりとしリラックスできて、夜もぐっすり眠ることができる。
「酒は百薬の長」ということわざがあるが、これに似たことわざは、海外にもいくつかある。
- 英語: “Wine is the best of medicines.”
この表現は、ワインが健康に良い薬のような役割を果たすという意味で、酒の健康効果を賛美している。他にも”Good wine makes good blood.”というのもあり、まさに私の血はワインで出来ていると言っていた、故・川島なお美さんの言葉を思い出させる。 - ラテン語: “In vino veritas.”
直訳すると「ワインに真実あり」という意味だが、酒が気分を和らげ、心の奥に隠れていたものが表に出るという点で、ある意味で「酒は心に良い影響を与える」という解釈もできる。ワインに真実あり、という場面を今まで何度も見てきた。これは確信できる諺である。 - フランス語: “Le vin est le plus sûr des remèdes.”
これは、「ワインは最も確実な治療薬である」という意味で、酒が健康に良い影響を与えるという考えに近いようだ。
これらのことわざは、酒が健康や人々の気持ちを高めるという点で「酒は百薬の長」に通じる部分がある。
ワインを日常的に飲んでいる地域は心筋梗塞になる人が少ない。特に「地中海ダイエット」として知られる食生活を送っている地域では、心筋梗塞やその他の心血管疾患の発症率が低いとされている。地中海地域(例えば、フランス、イタリア、スペイン、ギリシャなど)では、赤ワインを適量で飲むことが日常的な習慣とされており、この地域の人々は、心血管系に良いとされる健康的な食事(オリーブオイル、野菜、魚、ナッツなど)を摂取し、さらに赤ワインがその一環として取り入れられている。
赤ワインに含まれるポリフェノール(特にレスベラトロール)は、抗酸化作用があり、血管の健康を守る効果があるとされている。これが、心血管疾患のリスクを減少させる可能性があるという研究結果もある。
ただし、赤ワインの健康効果を享受するためには、言わずもがな適量を守ることが大切である。結論として、ワインを適度に飲んでいる地域では心筋梗塞が少ないというのは事実だが、それだけではなく、全体的な食生活や生活習慣も大きく影響しているようだ。
気付けば、私のダイエットは地中海ダイエットのそれである。赤ワインをたしなみ、食事にはオリーブオイルを使い、野菜をたっぷり食べ、オリーブ、ナッツをつまみにしている。だから、年齢の割には血圧も正常で、健康診断がオールAなのだろうか。。?
あともう一杯赤ワインを飲んでから本を読んでベッドに入ろう。
Have a good night!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44f7de6e.5496b3aa.44f7de6f.678be418/?me_id=1201918&item_id=10035963&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenoteca%2Fcabinet%2Fwine-set%2Fwine-set2%2Fwine-set9%2F25pb1-1_500b.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44f7de6e.5496b3aa.44f7de6f.678be418/?me_id=1201918&item_id=10035962&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenoteca%2Fcabinet%2Fwine-set%2Fwine-set2%2Fwine-set9%2F25pa2-1_500b2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
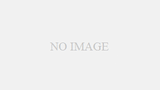
コメント